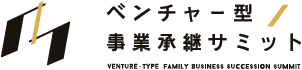様々な平面を、美しい立体に。技術と想いを再接続し、受託型から“共感でつながる”CAN製造メーカーへ。
課題:ルート営業と受託構造に依存し、新規展開が停滞。社員は「社長のお題待ち」状態に陥っていた。
その背景:BtoB受託生産が中心で、デザインは顧客主導。原材料高騰も重なり、原材料費高騰などの外部リスクが増加する中、現状維持の空気が組織を覆っていた。
資源:長年培った高い開発力と加工技術。金属に限らず、紙など多様な平面素材を美しい立体に成形できるノウハウを持つ。
着目点:「様々な平面を美しい立体にして届ける会社」として再定義。
缶を包装材ではなく、高付加価値な“主役”として社会に届ける視点を発見。
解決方法:社内公募制の「01Aプロジェクト」を発足。ワークショップで自走を促し、両面印刷の小型缶「コロン缶」と実店舗「カランコロン」を展開。
金属容器メーカーの生野金属は、高い技術開発力を持つ一方で、既存事業の安定感から成長が鈍化し、社員が経営者からの「お題待ち状態」にあるという閉塞感を抱えていました。また、新しい事業の種はあっても、それを世の中に広めていく「攪拌(かくはん)」する力が弱いという課題がありました。
SASIは、組織変革を支援の軸とし、「0を1にしてA(世の中に届ける)まで持っていく」ことを目指す「01Aプロジェクト」を立ち上げ、企業のアイデンティティを「様々な平面を美しい立体にして届ける会社」と再定義しました。
この変革を推進するため、組織全体を巻き込むワークショップ形式での伴走支援を実施し、社長(小西康晴氏)は、自らが答えを出すことを避け、社員の想いや考えを「共感の連鎖」として尊重し、引き出す役割に徹しました。
この結果、社員の意識が「やらされている」状態から「やりたい」という主体的な行動へと大きく変化し、プロジェクトに参画したパート社員が正社員登用を志願し、若手社員を中心に自ら考え行動する自⾛の文化が生まれ、組織の熱量が向上しています。さらに、社員の発案で生まれた小型缶「コロン缶」のリアル店舗「カランコロン」を、社員が主体となって企画・運営し、成功体験を共有することで、組織の熱量を高めています。
停滞する組織と「お題待ち」文化。動けない現場に、社長の焦りがあった。─ 課題と背景
生野金属は、業務用の一斗缶からお菓子の缶まで、多岐にわたる金属容器を年間1,200万缶以上製造する高い開発力と技術力を持つ企業です。しかし、原材料の高騰などの外部リスク、および既存顧客へのルート営業に頼る体制から、成長の鈍化を感じていました。新しい事業の種は社内にたくさんあったものの、それらをどう進めていいか分からず、活かしきれていない状態でした。小西社長が抱えていた最も大きな「強い違和感」は、組織の停滞感です。社員のモチベーションは低い(やる気がないのではなく、現状維持でいけてしまう感覚)と感じており、特に新規のアイデア出しにおいては、社員から自発的な意見が上がらず、「社長のお題待ち状態」となっていました。社内では「こんなことができるんじゃないか」という議論は意欲的にありましたが、社長以外に発信する人間がいなかったのです。社長は「このままだと、いつかは立ち行かなくなるだろう」という焦りを感じていたと言います。
「様々な平面を美しい立体にして届ける」──技術の本質を言葉に。─ アイデンティティの発見
SASIとの対話は、近畿経済産業局のデザイン経営支援事業への参加がきっかけで始まりました。ヒアリングとプロセスの中で、企業の本質的な強みとして見えてきたのは、過去から継承されてきた揺るぎない「開発力」です。かつて生野金属が缶の技術を活かし、電子レンジや電気ポットの外側フレームの製造を行っていた歴史(缶屋に特化していなかった歴史)も再認識されました。小西社長自身のイノベーティブな個性も整理の核となりました。そして、生野金属の企業アイデンティティ(ミッション)として、「様々な平面を美しい立体にして届ける」という一文が導き出されました。この定義により、社長自身が悩んでいた紙加工の新規事業も、「ミッションにブレてないやん」と確信を持って社内で説明できるようになりました。
技術と想いをつなぐ「01Aプロジェクト」。社員がつくる、缶の新しい物語。─ ブランド構築とデザインの意図
生野金属の技術(0→1)を、市場に広める力(1→A)に繋ぐために、SASIと共創して「01Aプロジェクト」という社内変革プログラムを立ち上げました。このプロジェクトの意図は、技術力はあるが、それを「届ける」部分(1→A)が弱いという課題を克服することにあります。施策として、まず両面にデザイン印刷が可能な手のひらサイズのミニ缶「コロン缶」の事業化に取り組みました。従来の缶が「包装材」「物流のための材料」であったのに対し、コロン缶はデザインそのものが価値となる「缶を主役にしたい」という思いから生まれました。コロン缶の販売を通じて、社員が「自ら発想した缶を世の中に出す」ことを体験することを目的とし、若手や部署を超えたメンバーを集めたワークショップ形式で推進。このプロセスを通じて、バリューを「缶製造メーカーからCAN(できる)製造メーカーへ」と再定義し、社内にクレドカードとして展開しました。
元パートの社員登用、若手の躍動。共感が連鎖する自走型組織へ。─ プロジェクトの影響
プロジェクトの後に生じた最も大きな変化は、社員の「主体性」の回復と「共感の連鎖」の発生です。ワークショップは当初、社員が社長の答えを探す状態から始まりましたが、社長が意図的に「私がしゃべったら答えになっちゃうから」と発言を抑え、社員の意見を尊重する姿勢を続けたことで、社員が自由に発言できるようになりました。具体的な成果として、コロン缶のリアル店舗「カランコロン」(缶にまつわる音を名前にした)が岸和田に誕生しました。そして驚くべきことに、このプロジェクトを通じて活躍した元パートの女性メンバーが、「私やりたいです」と自ら手を挙げ、社員登用されました。さらに、熱意ある若手の営業職の社員が中心となり事業を推進し、店舗では、顧客として来店していた女性が「ここで働きたい」と志願し、ペット(ポメラニアン)同伴でアルバイトとして入社するに至りました。また、外部からは特許庁が中小企業のデザイン経営の成功例としてこの取り組みに注目し、調査対象とするという評価も得ています。
クライアントの声
代表取締役の小西康晴さんは、SASIとの取り組みをこう振り返ります。
「企業って、数字だけじゃない価値があるっていうことだと思っていて、そのバリューがあるから、50年も70年も100年も続いてきたということを、今一度見直すことってすごく大事だと感じました」
「社内だけで同じプロジェクトってやっぱりできない。SASIのような、デザインや特定の切り口で入る伴走者がいてくれるから、成り立つと思います」
「SASIとの対話の中で、“様々な平面を美しい立体にして届ける会社”という言葉が出てきた瞬間、これやな、と思ったんです。
あの言葉があるから、社内に説明するときも“ミッションにブレてない”って言えるようになった」
企業、及びその経営者が、「自社のアイデンティティ」「未来のありたい姿」「社会的存在意義」を再定義するきっかけとなり、それらを見定めた上で、デザインの力を経営に活用することで、「ブランド力・イノベーション力」を高め、対外的には企業競争力の強化、
対内的には社員のモチベーション向上と「この会社で働く理由」を明確にすることができる点がすばらしい。